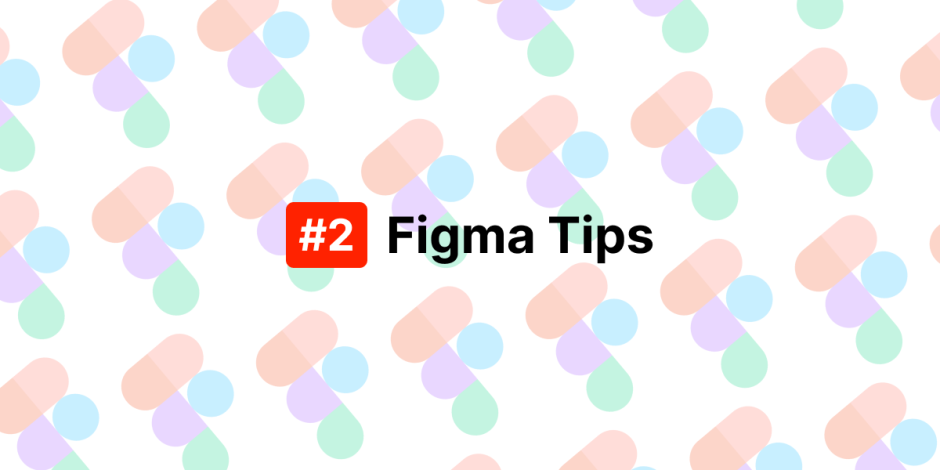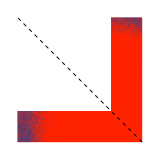Figmaは進化し続けており、フリーランスデザイナーとしてその最前線に立つことは、競争力を維持し、効率を最大化する上で不可欠です。#2では、#1で紹介した基本をさらに深掘りし、最新のFigma機能とより高度な実践テクニックを盛り込むことで、皆さんのデザインワークフローを一段と強化します。
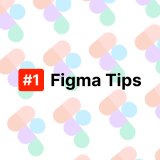 Figmaをフリーランスデザイナーが最大限に活用するTips集 #1
Figmaをフリーランスデザイナーが最大限に活用するTips集 #1
1. 最新Figma機能の活用でデザインを高速化
Figmaの最新機能を使いこなすことで、作業効率とデザインの質を向上させ、競合との差別化を図れます。
a. Variables (変数) を使ったテーマ管理と多言語対応
FigmaのVariablesは、カラー、数値、文字列などを変数として定義し、デザインに適用できる強力な機能です。特にダークモードの切り替えや多言語対応、レスポンシブデザインにおいて真価を発揮し、手動での修正作業を劇的に減らします。
具体的な活用イメージ:
- ライト/ダークモードの切り替え:
--color-primary-text-light(白背景での文字色) と--color-primary-text-dark(黒背景での文字色) のように、テーマごとの色を変数として定義します。- コンポーネントにこれらの変数を適用しておけば、デザインファイル全体でワンクリックでライトモードとダークモードを切り替えられます。クライアントへの提案時も、両方のテーマを瞬時に見せることが可能です。
- 多言語UIの効率化:
- 「Hello」というテキストを変数
--text-greeting-en、「こんにちは」を変数--text-greeting-jpとして設定します。 - ボタンや見出しなどのテキストレイヤーに変数を適用すれば、ファイルのプロトタイプ設定で言語を切り替えるだけで、瞬時にUIテキストが変更されます。翻訳の変更があった際も、変数を更新するだけで済み、手動でのコピペ作業が不要になります。
- 「Hello」というテキストを変数
- レスポンシブデザインの最適化:
--spacing-desktop(24px) と--spacing-mobile(16px) のように、デバイスごとの余白の値を定義します。- Auto Layoutの余白にこれらの変数を適用すれば、デスクトップ用とモバイル用のデザインを同じコンポーネントインスタンスで管理でき、デザインの複製や修正の手間を省けます。
b. コンポーネントプロパティで柔軟なコンポーネントを構築
Ver.1で触れたコンポーネントをさらに進化させるのがコンポーネントプロパティです。これにより、バリアントの数を劇的に減らし、コンポーネントをより柔軟に、より少ない労力で管理できるようになります。
具体的な活用イメージ
- テキスト変更の簡易化
- ボタンコンポーネントに**「Label」というテキストプロパティ**を設定します。
- デザインボード上のボタンインスタンスを選択するだけで、プロパティパネルから直接ラベルテキストを編集できます。
Button/Primary/Default/Label: Click Hereのように、バリアントを増やすことなく多様なテキストを扱えます。
- アイコン表示のオン/オフ切り替え
- 入力フィールドコンポーネントに、「Show Left Icon」や「Show Right Icon」といったブール値プロパティ(真偽値、チェックボックスでON/OFF)を追加します。
- チェックボックスをオンにするだけでアイコンが表示され、オフにすると非表示になります。これにより、「アイコンあり」「アイコンなし」のバリアントを別途作成する必要がなくなります。
- コンポーネント内の要素入れ替え
- カードコンポーネントのヘッダー部分に、「Header Type」というインスタンススワッププロパティを設定します。
- これにより、そのカードのヘッダー部分を「Text Header」コンポーネントから「Image Header」コンポーネントに、プロパティパネルから簡単に切り替えられます。アイコンセット内のアイコンを入れ替える際にも非常に便利です。
2. 実用的なデザインシステム構築法
フリーランスとして、効率的なデザインシステムは、複数のクライアントやプロジェクトで一貫性と品質を保つための生命線です。単なるコンポーネント集ではなく、拡張性と引き継ぎを意識したシステムを構築しましょう。
a. チームライブラリと組織的な運用(ソロでも実践)
もし複数のデザイナーと協力したり、将来的にチームを拡大する可能性があるなら、Figmaのチームライブラリを効果的に活用しましょう。一人で運用する場合でも、将来の引き継ぎや自身のプロジェクト横断での再利用性を高めるために非常に有効です。
具体的な活用イメージ
- 共通デザイン資産の公開
- 「My_Design_System.fig」というマスターファイルを作成し、よく使うボタン、テキストスタイル、カラーパレット、アイコンなどをここに集約します。
- このファイルをライブラリとして公開すれば、新しいプロジェクトファイル(例:「Client_A_LP_Design.fig」)から、そのマスターファイルのコンポーネントやスタイルを自由に利用できるようになります。
- 変更管理の明確化
- マスターファイルを更新した際は、必ずライブラリの変更を公開し、変更内容を具体的にコメントします(例: 「v1.2: プライマリボタンのホバー色を修正、新しいインプットフィールドを追加」)。
- これにより、他のファイルでライブラリを更新する際に、何が変わったのか一目で理解でき、意図しないデザイン崩れを防げます。
b. コンポーネントの階層化と命名規則の洗練
大規模なデザインシステムを構築する際には、コンポーネントの命名規則と階層化が非常に重要になります。特に**Atomic Design(アトミックデザイン)**の概念を取り入れると、エンジニアとの連携もスムーズになります。
具体的な活用イメージ
- Atomic Designに基づく設計
- Atoms(原子): ボタン (
Button/Primary), アイコン (Icon/Arrow), 入力フィールド (Input/Textfield) など、最小単位のコンポーネント。 - Molecules(分子): 検索ボックス(入力フィールド+ボタン)、ナビゲーションリンク(アイコン+テキスト)など、Atomsを組み合わせたもの。
- Organisms(生体): ヘッダー、フッター、商品リストなど、MoleculesやAtomsをさらに組み合わせて、特定の機能を持つUIの塊。
- このように体系的にコンポーネントを設計することで、複雑なUIも構造的に理解しやすくなり、再利用性が格段に向上します。
- Atoms(原子): ボタン (
- 意味のある命名規則の徹底
ComponentType/Name/Variant/Stateのような命名規則を採用します。- 例:
Button/Primary/Large/Hover,Input/Text/Default/Placeholder。 - Figmaのアセットパネルで階層的に表示されるため、必要なコンポーネントを直感的に探しやすくなります。
3. クライアント・開発者との連携を強化するFigma術
スムーズなコミュニケーションは、プロジェクト成功の鍵です。Figmaの共有機能を最大限に活用し、クライアントや開発チームとの認識齟齬をなくしましょう。
a. Dev Modeを最大限に活用し、開発者との連携を加速
Dev Modeは、デザイナーと開発者の連携を劇的に改善する機能です。開発者に必要な情報(CSS/iOS/Androidコードスニペット、アセットのエクスポートなど)をFigma内で直接提供できます。
具体的な活用イメージ
- 正確なスペック情報の共有
- 開発者はDev Modeに切り替えるだけで、選択した要素の正確なサイズ、余白、カラーコード、フォント情報などを確認できます。
- 特にAuto Layoutで適切に設計された要素は、paddingやgapなどの値がそのままCSSとして表示されるため、開発者は直感的にレイアウトを再現できます。手動での数値入力ミスが激減します。
- アセットエクスポートの自動化
- デザインしたアイコンやイラストをエクスポート設定しておけば、開発者はDev Modeから必要な形式(SVG、PNG、JPGなど)で一括ダウンロードできます。
- 「アイコンの抜け漏れ」「サイズ違い」といったミスを防ぎ、開発チームの手間を省きます。
- コメントによる議論の集約
- Dev Modeでもコメントを残せるため、特定の要素に関するデザインと開発両面からの疑問や提案をFigma内で集約できます。
- 「このアニメーションの速度はどうしますか?」「この要素はレスポンシブでどう表示されますか?」といった議論が、デザインファイル上に履歴として残ります。
b. プロトタイプを活用した効果的なフィードバック収集
Ver.1で触れたプロトタイプは、単なる動きの確認だけでなく、ユーザーテストやクライアントからの具体的なフィードバック収集に役立ちます。
具体的な活用イメージ
- ユーザーテストの実施と改善点洗い出し
- 作成したプロトタイプをターゲットユーザーに操作してもらい、Figmaのコメント機能や**外部のユーザーテストツール(例:Maze, UserTesting)**と連携して、使いづらい点や迷った点を洗い出します。
- 実際のユーザーの反応を基に、客観的な改善点を見つけ出し、説得力のある提案に繋げられます。
- クライアントへの「触れる提案」
- 完成したデザインを画像で送るだけでなく、実際のWebサイトやアプリのように操作できるプロトタイプを提供します。
- 「このボタンをクリックすると、次の画面に遷移します」「入力フォームでエラーが出た場合の表示はこちらです」といった具体的な動きを体験してもらうことで、認識のズレを最小限に抑え、具体的なフィードバックを引き出しやすくなります。
Ver.2のTips集は、Ver.1の土台の上に、Figmaの最新機能とフリーランスとしてのより高度な実践例を積み重ねたものです。これらの情報を活用し、皆さんのデザインワークとビジネスがさらに発展することを願っています。