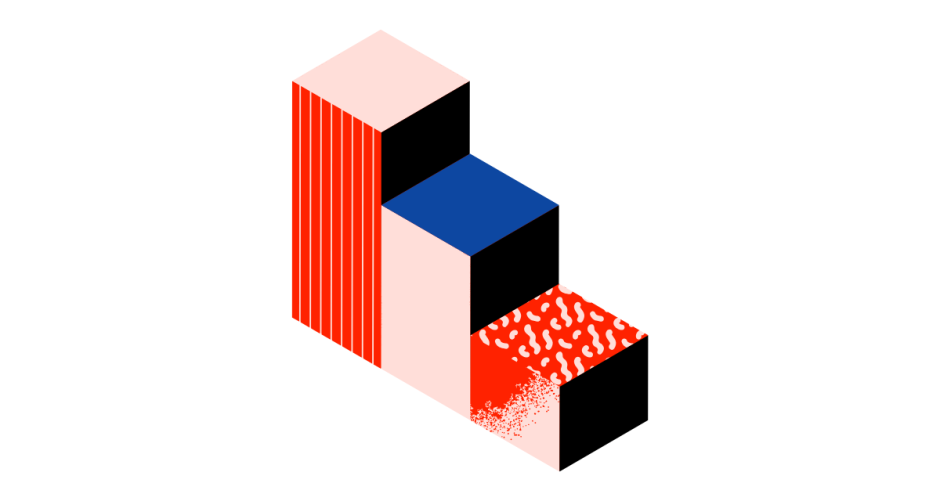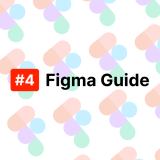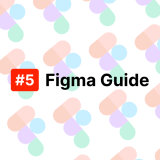こんにちは。この記事を書いているのは、かつてはWebディレクターとして働き、現在はフリーランスのUI/UXデザイナーのてらしいと申します!大学で建築系を専攻していた私が、社会人最初の仕事はITメガベンチャーでのWebディレクターでした。そこから転職や副業を通してデザインのスキルを伸ばし、今では独立しています。
デザイナーとして独立することは、多くの不安や疑問を抱えるものです。私自身もその一人でした。この記事を通じて、その不安や疑問を少しでも解消し、具体的な行動に移せるようになればと思います。具体的には、どのようにスキルを習得すればよいのか、どのツールを使えば効率が良いのか、どうすれば初めてのクライアントを獲得できるのか、といった疑問に答えていきます。
「フリーランスUI/UXデザイナーになりたいけど、何から始めればいいかわからない」 「本当に未経験からなれるの?」 「スキルを習得する具体的なステップが知りたい」
もしあなたがこのような悩みを抱えているなら、この記事がきっと役立つでしょう。未経験からフリーランスUI/UXデザイナーを目指す際の全体像と具体的なロードマップを、ステップバイステップで解説します。
1. UI/UXデザイナーという仕事のリアル
まず、UI/UXデザイナーとはどのような仕事なのか、その魅力や市場価値について理解を深めましょう。
1-1. UI/UXデザインの仕事内容とは?
UI/UXデザインは、製品やサービスの**ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)**を設計する仕事です。
- UIデザイン:ユーザーが直接触れる部分(ボタン、メニュー、レイアウト、フォント、配色など)のデザインに関わります。見た目の美しさだけでなく、視認性や操作性も重要になります。
- UXデザイン:ユーザーが製品やサービスを使用する全体的な「経験」を設計します。ユーザーが目的を達成するまでのプロセス全体(利用前の期待、利用中の感情、利用後の満足度など)をより良くするための設計です。
簡単に言えば、UIは「どう見えるか」、UXは「どう感じるか」をデザインすると考えると分かりやすいでしょう。両者は密接に関わっており、どちらか一方だけでは優れたプロダクトは生まれません。
1-2. UI/UXデザイナーの市場価値と求人状況
UI/UXデザイナーの需要は世界的に高まっています。CareerFoundryによると、UI/UXデザイナーは平均で年間$85,277(約920万円)を稼いでいます。日本でもDIGIDAY[日本版]が報じているように、UI/UXデザイナーの需要は高まっており、特にフリーランスとしての活躍の場が広がっています。
フリーランスとして働くデザイナーにとって、求人の数と質は非常に重要な指標です。特にUI/UXデザイナーやプロダクトデザイナーといった職種では、国内でも多くの求人が出ています。具体的な数は時期や求人サイトによって異なりますが、数百から数千件の求人が掲載されていることも少なくありません。
どのような求人が多いのか?求人内容を見ると、スタートアップから大手企業まで、多様な業界でデザイナーが求められています。また、リモートワークの選択肢も増えており、地域に縛られずに働くことが可能です。
求人を探す際には、自分のスキルセットや希望する働き方に合ったものを選ぶことが重要です。LancersやCrowdWorksなどの国内のフリーランス求人サイトを活用すると、常時数百件以上の求人があります。
このように、国内でもフリーランスデザイナーとして多くの機会があります。しかし、多くの求人がある一方で、競争も激しいため、スキルと経験をしっかりと積んでおくことが成功の鍵です。
2. 未経験からUI/UXデザイナーになるのは難しい?必要なスキルと心構え
「デザイナーは才能が必要」「未経験では無理」といった声を聞くかもしれません。しかし、結論から言うと、UI/UXデザイナーになるのに才能は不要です。必要なのは、論理的な思考力と地道な努力、そして「ユーザーのために何ができるか」という視点です。
2-1. UI/UXデザイナーに求められるスキル一覧
UI/UXデザイナーは、単に絵を描くだけではありません。多岐にわたるスキルが求められます。
- 要件整理・ヒアリング能力
クライアントやユーザーの「本当にやりたいこと」や「困っていること」を引き出し、デザインの要件として明確にする能力。 - ユーザーリサーチ
ターゲットユーザーの行動、ニーズ、課題を深く理解するための調査能力(インタビュー、アンケート、データ分析など)。 - 情報設計(IA:Information Architecture)
サービス内の情報を分かりやすく整理し、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるような構造を設計する能力。サイトマップやユーザーフローの作成が含まれます。 - UXフロー作成
ユーザーがサービス内でどのような経路をたどるか、その体験の流れを設計・可視化する能力。 - ワイヤーフレーム作成
UIの骨組みを視覚的に表現し、情報配置や機能要素を検討する能力。 - プロトタイピング
デザインの初期段階で動作するモックアップを作成し、ユーザーテストや関係者とのコミュニケーションに活用する能力。 - UIデザイン・ビジュアルデザイン
実際にユーザーが触れる画面のデザイン能力(レイアウト、配色、タイポグラフィ、コンポーネント設計など)。デザインシステム作成能力も含まれます。 - デザインシステム作成
一貫性のあるデザインを効率的に作成・管理するためのルールやガイドライン、再利用可能なコンポーネント集を構築する能力。 - ユーザーテスト
作成したプロトタイプやサービスを実際にユーザーに使ってもらい、課題や改善点を発見する能力。 - 分析・改善提案
デザインの効果を数値や定性データで分析し、継続的な改善提案を行う能力。 - コミュニケーション能力
エンジニア、ディレクター、クライアントなど、多様な関係者と円滑にコミュニケーションを取り、デザインの意図を伝え、合意形成を行う能力。
これらのスキルを未経験からすべて完璧に習得するのは困難です。しかし、ロードマップに沿って段階的に学ぶことで、着実に力をつけることができます。
2-2. 未経験人材がスキルを獲得するための学習とアウトプット
未経験からこれらのスキルを獲得するためには、座学だけでなく、手を動かしてアウトプットを重ねることが最も重要です。
- インプット(学習)
- オンラインコース・動画教材
Udemy, YouTube, Schooなど、体系的に学べるプラットフォームを活用します。特に、実践的な内容が多いものを選びましょう。 - 書籍
UI/UXデザインの基礎理論や思考法を学ぶのに役立ちます。『About Face』などの名著を読むのも良いでしょう。 - デザイン関連ブログ・記事
Goodpatch Blogやferretなど、最新のトレンドや実践事例を学ぶのに適しています。
- オンラインコース・動画教材
- アウトプット(実践)
- UIトレース
既存の優れたUIをFigmaなどのツールで模倣し、レイアウトやコンポーネントの使い方を体で覚えます。 - 架空のサービスデザイン
自分でテーマを設定し、ユーザーリサーチから情報設計、UIデザイン、プロトタイピングまでの一連のプロセスを経験します。 - 課題解決型デザイン
身の回りにあるアプリやウェブサイトの「使いにくい」と感じる部分を見つけ、自分なりに改善案をデザインしてみる。なぜ使いにくいのか、どうすれば改善できるのかを論理的に説明できるようにします。 - ポートフォリオ作成
学習したこと、作成したアウトプットを体系的にまとめ、自分のスキルと思考プロセスを可視化します。
- UIトレース
2-3. 近道は「Figma」の習得から
UI/UXデザインの学習において、最も近道であり王道と言えるのがFigmaの習得です。Figmaはクラウドベースのデザインツールで、多人数でのリアルタイム共同作業に優れています。プロトタイピングからUIデザインまで、UI/UXデザインに必要な機能がほぼ網羅されており、多くの企業やフリーランスデザイナーが活用しています。
Figmaを使いこなせるようになれば、アイデアを素早く形にし、プロトタイプとして動かし、フィードバックを得て改善するというデザインプロセスを効率的に回すことができます。まずはFigmaの基本操作から習得し、手を動かしながら学ぶ環境を整えましょう。
Figma guideを参考にぜひFigmaを習得してみてください!
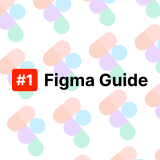 Figmaマスターへの道 #1:未経験からUI/UXデザイナーになったフリーランスが語る、Figmaを制する者がデザインを制する理由
Figmaマスターへの道 #1:未経験からUI/UXデザイナーになったフリーランスが語る、Figmaを制する者がデザインを制する理由
3. フリーランスUI/UXデザイナーになるためのロードマップ全体像
未経験からフリーランスUI/UXデザイナーを目指すためのロードマップは、以下のステップで構成されます。これらのステップを踏むことで、クライアントや企業が求めるUI/UXを設計できる人材になるためのスキルを身につけられます。
【ロードマップの全体と想定期間】 学習期間の目安は週12時間以上を最低デザイン学習の時間に当てられることを想定しています。
- デザインツール「Figma」の習得
- デザインの基本知識
- デザインをする基本スタンス
- インターフェースの基本
- 情報設計の基本
- 顧客理解と課題解決の基本
基礎理解で作成したものをベースに、アピールするアウトプットを仕上げる
営業戦略の立案、求人サイトの活用、コミュニティ参加
目指すデザイナー像とそのレベル
このロードマップで目指すスキル像は、ただ言われたものをUIにするようなデザイナーではありません。現場では事業貢献が求められます。そこにUIデザインを通して貢献できる素養がある基礎レベルを目指します。また、未経験から現場に入る人も想定をしているため、継続的に学習していける学習素養や、問題なく意思疎通を現場のメンバーと行うコミュニケーションスキルの習得も視野に入れています。
目指すレベルの6つの特徴
- 顧客視点を持ち、課題解決を軸にデザインする素養がある
- 必要最小限のデザインツール操作に習熟している
- 顧客にとっての“使いやすさ”を設計する基礎的なUI情報設計スキルがある
- 基礎的なUIパターンとガイドラインを理解している
- 制作過程や意図を言語化・共有できる
- 現場メンバーの考えを理解し意思疎通できるコミュニケーションスキルがある
- 継続的な学習意欲と業界トレンドのインプットが欠かせない
4. ロードマップ詳細:各フェーズでやるべきこと
ここからは、各フェーズで具体的に何を学ぶべきか、どのように進めるべきかを詳しく解説します。
フェーズ1. デザインを始める:基本ツール習得とマインドセット
このセクションでは、まずFigmaといった基本的なデザインツールの操作から始めます。未経験者が最初に覚えるべきは、画面作成の流れやパーツ配置、プロトタイプ設定など、最低限の機能理解です。UIをツールを使ってデザインする方法から始めて、デザインツールに慣れることから始めましょう。
加えて、デザイン自体の基本スタンスも重要です。たとえば、グラフィックデザインの基本である色・余白・タイポグラフィといった基本要素や、上達するデザイン制作の基本の流れを一度通っておくと、デザイン学習に対するイメージを持ちやすいでしょう。
ここでの目標は、いきなり高度なUI/UX理論に突入するのではなく、「手を動かしながら学べる環境」をつくること。ツール操作と基本的な視点を身につけることで、次の段階であるUI/UXの3基礎を理解する土台ができます。
フェーズ1で目指す状態
- FigmaでUIをデザインできるようにする
UIデザインツールの定番、Figmaの操作に慣れてUIを作れるようになりましょう。 - デザイン学習の基礎を抑える
UI/UXの基礎スキルに入る前に、デザインの基本原則とデザインスキルを身につける上でのスタンスを習得して、デザインスキルを身につける土台を固めます。 - UI/UX学習のゴールを持つ
UI/UXデザイン学習のゴールは「ポートフォリオを作ること」です。基礎を身につける目的もまずはそこがゴールになるため、本格的なUI/UXの学習に進む前にそのゴールをイメージを持ちましょう。
4-1-1. 【習得1.】Figmaの基本操作を習得
Figmaを使いこなして、UIデザインの下地を固めよう! UIデザインの学習を始めるにあたって、ツールを使えることはとても大切です。UIやWebサイトのデザインに最適なFigmaの使い方に慣れるところから始めましょう。
このパートのゴール
- Figmaの使い方に慣れよう
まずはFigmaの操作に慣れるところから始めましょう。UIをトレースしながらで良いので、UIの見た目をFigmaで再現しながら基本的な使い方を覚えて慣れていくのが効果的です。機能もオートレイアウトとプロトタイプ機能までは最初のうちに使えるようになっておきましょう。 - UIを作れる実感を得る
UIが完成した達成感と、将来の仕事にどうつながるかが少しずつ見えてくるようになり、モチベーションが高まります。これから本格的にデザイン、UI/UXをやっていく上でもツールの操作ができているとスムーズに進むことができます。
Figmaの基本操作を身につけよう
- UIトレースで基本操作に慣れる
他のサービスのUIを真似してみる「UIトレース」は、ボタンやレイアウトを模倣するうちに自然と機能を覚えられる定番の学習手法です。色やテキストスタイルを何度も設定していくうちに、ショートカットキーなども体感的に身につけられます。多くのWebサイトやアプリのUIをFigma上で再現してみる練習を重ねましょう。 - オートレイアウト機能を覚える
Figmaのオートレイアウト機能の使い方を身につけましょう。オートレイアウトは、要素の配置や余白をシステマチックに管理できる機能で、レスポンシブデザインの作成やコンポーネント化に不可欠です。実際のコードでのレイアウトの考え方にも直結するため、早めに習得し、慣れておくことが重要です。 - プロトタイプの扱いを覚えて、動きのあるUIを作る
Figmaにはクリックして画面を遷移を擬似的に表現して確認できる「プロトタイプ機能」があります。UIは絵ではなく操作して体験することが主な目的です。そのため、プロトタイプ機能で画面遷移を設定して“実際の使い心地”をテストすることがUIのクオリティにもつながります。ユーザーテストやプレゼンテーションで非常に役立ちます。
Figmaの基礎が学習できるコンテンツ(例:Udemy、YouTube、Figma公式チュートリアルなど)
- Udemyなどのオンラインコース
Figmaの初心者向けコースが多数提供されています。体系的に学びたい場合に最適です。 - YouTubeのチュートリアル動画
無料で多くのFigma使い方解説動画があります。「Figma 使い方」「Figma 初心者」などで検索し、実際に手を動かしながら学習しましょう。 - Figma公式ヘルプ・チュートリアル
Figmaが提供している公式のドキュメントやチュートリアルも非常に分かりやすく、信頼性が高い情報源です。
4-1-2. 【習得2】デザインの基本とスタンスを得る
デザインの4原則、上達方法、制作の基本、UI/UX学習のゴールを抑えよう UIデザインを始めたばかりの段階で、いきなり独創的な作品を目指すのはハードルが高いもの。実はプロのデザイナーも、定番の配置や色使いを活用して「見やすさ」「使いやすさ」を担保していることが多いのです。それをどう学ぶか?理論だけではなく世の中のふつうのデザインを真似したり、制作を重ねることで学習しアウトプットのクオリティが上昇していきます。
このパートでは、基本となるデザイン原則を押さえつつ、いわゆるふつうのUIを真似することや、UIに限らないデザイン制作の基本の流れを身につけることを目標にします。また、最終的なUI/UX転職に必要なゴールを認識することで、ロードマップに必要なスキルの意味や最終目標を理解して効率をUPさせておきましょう。
- デザインの基本原則、盗み方、制作の流れ
文字の読みやすさや余白の取り方など、基礎的な美的ルールを理解して“定番UI”を作り込めるようになる。また「ふつうのUI」を真似して世の中のデザインから盗んで学習する姿勢が大切です。最初から独創性を追いかけるよりも、成功事例を自分の中に落とし込むことで成長を早める。そして最後にデザインを作って検討する基本的な流れを知って自分で実践できるようになりましょう。 - UI/UX学習のゴール把握
転職するならポートフォリオが必要。最終的にどんなことをアピールする必要があるのかをUI/UXの本格学習に進む前に把握しておきましょう。
デザインの基本とスタンス「4つのポイント」を身につけよう
- デザイン基本原則をインプットしておく
- デザインの4原則の習得
表現デザインの基本である「近接」「整列」「反復」「対比」について学びましょう。これらの原則を理解することで、なぜそのデザインが良いのか、悪いのかを論理的に説明できるようになります。 - 色彩とタイポグラフィの基礎:
UIデザインにおける色の使い方(機能と感情)や、フォントの選び方、文字の読みやすさを確保する方法を学びます。
- デザインの4原則の習得
- 「ふつうのUI」を真似して上達するスタンスを持つ
- 参考デザインから盗む方法
UIデザインは「構造」「機能」「見た目」の3要素に分解してデザインを参考にすると扱いやすいです。その盗む目の基本や、UIを普段から見ておくためのデザインの探し方を把握して、日頃からデザインを吸収できる土台を作りましょう。DribbbleやBehanceなどのデザインギャラリーサイトや、様々なアプリを実際に使ってUIの良い点・悪い点を分析する癖をつけましょう。
- 参考デザインから盗む方法
- デザイン制作の基本の流れを知っておく
- リサーチ → ラフ設計 → パターン出し → 検討評価 → ブラッシュアップ:デザインを作る時は最初はアイデアを広げて徐々に収束する形で検討していくのが基本です。こうすることで適切なアイデアをまず模索し、正しい方向性の表現の質を高めて仕上げていく基本が身につきやすいです。また自分で自分のデザインを評価するスキルを磨くことはデザインを見る目の向上にもつながる大切な要素です。
- UI/UXデザイナー転職のゴールイメージを知っておく
- ポートフォリオ
実際に作ったUIやプロセスをまとめて公開することで、自分の強みをアピールできる、採用に応募する時に必須になるものです。デザインスキルは採用の足切り要素として機能します。 - 会社や必要スキルの理解
制作会社なのか、事業会社なのかなどの会社の特徴や、テック業界の会社を知る方法、またロードマップの元になっている、どういうスキルや内面が採用では評価されるのか、未経験者は特にどういう工夫があると受け入れやすいのかを理解しておくと、学習しながら採用で見せるスキルや素材を貯めながら計画的に学習できる確率が上がります。
- ポートフォリオ
「デザインの基本とスタンス」に役立つコンテンツ(例:書籍、オンライン学習プラットフォーム)
- 書籍
「ノンデザイナーズ・デザインブック」「デザインの原則」など、デザインの基礎原則を学べる書籍を読みましょう。 - オンラインコース
デザインの基礎を学べるコースを選びましょう。UdemyやSchooなどで「デザイン基礎」「Webデザイン入門」といったキーワードで検索してみてください。 - デザインギャラリーサイト
Dribbble, Behance, Mobbin, Lapa.ninja などで優れたUIデザインを日々インプットし、なぜそれが優れているのかを考える習慣をつけましょう。
次のステップ
ここで固めた「デザインの基本」「ふつうのUI」「ゴールイメージ」の3つは、今後の学習で何度も役立つ土台になります。 引き続き、UI/UXの3基礎(インターフェース、情報設計、課題解決)を身につけるフェーズへ進みましょう。
定番の手法や考え方をベースに、自分のアレンジを効かせられるようになったとき、UIデザインの面白さがさらに広がっていきます。
フェーズ2. UI/UXデザイン3つの基礎を習得
ここでは、UI/UXを理解するうえで欠かせない3つの基礎要素をコンパクトに紹介します。1つ目は「インターフェース基礎」で、ユーザーが迷わず操作できる画面要素や一貫性・視認性の確保、基本的なUIパターン理解を示します。2つ目は「情報設計基礎」で、ユーザーが求める情報を適切に構造化し、流れを設計する考え方。
3つ目は「課題解決基礎」で、ユーザーの課題を発見し、改善策を発想・検証する流れを学びます。ここでは詳細な理論で圧倒しないよう、キーポイントを示すに留めます。深い学習は別記事や学習リソースへつなげ、まずは「UI/UXはこの3軸で考える」と理解できれば十分です。
このフェーズで目指す状態
- UIを使って顧客の課題解決をするための、最低限必要な「3つの基礎」を習得する
- UIデザイナーの役割はただ言われたことをUIにするだけの作業的なデザイナーではありません。デザインを武器に、ユーザーが価値を感じるデジタル上の体験を設計するために仕事をすることになります。価値をUIを通して実現するために「3つの基礎」が必要だと考えています。
- インターフェースの基礎
これはUIの見た目をつくるためのUIデザインの基本になります。UIの見た目を構築する「UIビジュアル基礎」と、UIを操作して基本的な体験を実現する「UI操作の基礎」の2つに分けて考えていきます。 - 情報設計の基礎
ユーザーはこういうことをしたいからこういう操作や処理をする必要がある、という状態からUIのアイデアを出して体験をデザインする基本を身につけます。実際の業務に最も近い内容です。ユーザーや現場の課題や要件、やりたいことをベースに、そのユーザーにとって使いやすいUIとその体験の形を具体化していくUIデザインの手法です。 - UXデザインの基礎
顧客のことを理解して顧客の課題を解決するための体験をデザインする基礎を身に付けます。ただUIを作るのではなく”なんのために”、”誰のため”のUIなのかを考えるには、顧客そのものの理解をする経験が不可欠です。少し上流の考えでUI制作からは遠く感じるかもしれませんが、自分が作るUIが誰の何のためになっているのか?を身につける体験設計、課題解決の基本を学びます。
4-2-1. 【習得1】インターフェース基礎
インターフェース基礎を押さえて、使いやすいUIを実現できるようになろう! UIデザインを学び始めたばかりの方にとって、最初の大きなハードルになるのが「インターフェース基礎」です。画面をどう構成するのか、ボタンやナビゲーションをどこに置けばユーザーが迷わず操作できるのか、そもそもUIの見た目をどう考えて構築するのか…そんな疑問を解決する土台となるのがこのパート。ここをしっかりと理解しておくと、後から出てくる高度な情報設計やUXデザインの学習もグッとラクになります。
このパートのゴール
理解を確認するためには実際にUIを作りデザインすることが必要です。これらの基礎を使って「SNSアプリ」や「Todoサービス」の基本機能をすべてデザインすることで基礎概念を使用したUIデザインを一度自分で実践できます。理解が深まるでしょう。 UIは絵ではなく操作してある体験を提供することで初めて意味を持ちます。なのでこのパートでは基本的な操作をするUIを自分で作れるようになること。そのための基礎知識を身につけて実践しアウトプットすることをテーマにします。
インターフェースの基礎「3要素」を身につけよう
以下の3つを身につけて、”ふつう”のUIの仕組みを学びつつ習得することがゴールです。
- UIを構成するビジュアルの基礎
- UIの見た目の構成要素
フォントや色、要素の大きさ、余白の取り方など、ビジュアルデザインの仕組みをUIデザインのケースで、仕組み化してコントロールする基本を学びましょう。見た目を構成する要素を1つずつ習得することで、UI自体を見る目の解像度が高まります。 - 要素の因数分解
タイポグラフィ / 配色 / 余白 / ディスプレイとスクリーンサイズ / 構造・ブロック / 階層などを理解します。
- UIの見た目の構成要素
- UIの状態変化の基礎
- 基礎状態変化
エラー表示やホバー時の反応など、ユーザーの行動や状況に応じてUIが変わる場面もあります。こうした”状態”で変化するUIの基本を習得しましょう。「新規作成」「閲覧」「編集」「削除」など、よくある操作パターンで変化するUI表現について学びます。 - コンポーネント
また状態変化に合わせてUIの「コンポーネント」という概念の基本についても学びましょう。コンポーネントとはソフトウェア上でUIパーツを使い回す概念のことです。この利点や、違う画面でも同じ役割や状態を示すUIについて学びましょう。
- 基礎状態変化
- UIの操作の基礎:
- UIの操作の基礎
UIは絵ではなく操作する体験を形作って初めて意味をなします。そのUI操作に必要な基礎概念について抑えましょう。 - UIとモード
ソフトウェアの操作中に”ある状態に集中する”状態をユーザーに与える「モード」という基礎概念について理解しましょう。主に「作成↔︎閲覧」モード、「選択」モードなどを例に理解して行きます。 - UIとナビゲーション
ユーザーに現在地や前にいた場所、サービス内で可能な操作など、機能のヒントを与えるために重要な「ナビゲーション」について学びましょう。基本的な役割とナビゲーションパターンを抑えて行きます。 - UIとアクション
UIにおける「アクション」の概念について学びましょう。適切なアクションの配置や、操作する対象の”オブジェクト”と操作ボタンの位置関係など、基本的に使いやすいアクションについて学びましょう。
- UIの操作の基礎
インターフェースの基礎を身につけられる解説&実践コンテンツ(例:書籍、オンラインコース、デザインガイドライン)
- 書籍
「UIデザインの教科書」「WebサービスのUIデザイン」など、UIの構成要素や操作性を実践的に学べる書籍を活用しましょう。 - デザインシステムガイドライン
Google Material DesignやApple Human Interface Guidelinesといった、主要なデザインシステムを参考にしましょう。これらのガイドラインは、なぜそのUIがそうあるべきなのか、という理由付けまで含めて学べます。 - オンラインコース
UIビジュアルデザインやインタラクションデザインに特化したコースを受講しましょう。実際に手を動かしながらUIを作成する課題があるコースがおすすめです。
4-2-2. 【習得2】情報設計の基礎
情報設計の基礎を押さえて、顧客に寄り添ったUIを実現できるようになろう! UIデザインで画面の見た目だけ作れるようになっても意味がないです。実際の業務では、「提供するサービス機能をどう画面に落とし込むか?」「ユーザーはどんな操作がイメージしやすいか?」を考えてUIのアイデアを操作の流れと一緒に考えて行きます。つまり、要件や課題をクリアにし、それをUIにきちんと反映させていく力がとても重要です。
このパートでは「要件 → UIのアイデア → ユーザー体験」という流れを筋道立てて考える方法を身につけます。ここをしっかり学べば、プロダクト開発の要望を“使いやすい画面”に落とし込む基礎ができあがり、より実践的なUIデザイン力が養われます。
「要件をもとにUIアイデアを具体化する」フローを通じて、ユーザーにとって最適な操作や画面構成を導き出せるようになる。なぜそのUIが必要なのか?をユーザー・要件を軸に論理的に考えるデザインフローを習得することに繋がります。 少し複雑なソフトウェアのアイデアを、機能アイデアだけの状態から、ゼロから自分で作成することで、ユーザーと要件を満たすUI作成の流れを身につけることができるでしょう。
情報設計の基礎を身につけよう
- UIモデリング
- UIの要件定義
要件を理解→分解しUIに落とす整理するやり方を身につけよう。作るべき機能の内容だけを考えるのではなく、ユーザーを主語に「ユーザーが何をしたいのか」「何に困っているのか」「どういう操作が必要か」を整理し、それを叶えるために必要な、ユーザーの行動の流れや画面に必要な情報などを洗い出します。 - OOUI(オブジェクト指向UIデザイン)
画面を単に「ページ」として見るのではなく、「ユーザーが扱うオブジェクト」に着目して整理すると、機能や情報の優先度をより論理的に決められます。UIの情報設計の基本でオブジェクト中心のやり方を学びましょう。
- UIの要件定義
- UIプロトタイピング
- プロトタイピング概念の理解
デザインの強みは完成・リリースする前に具体的な形を作って効果的かどうかを検討できる、点です。40%〜ぐらいの完成度で、達成するべき要素を満たせる具体的な形をパターンを作って検討することを「プロトタイピング」と呼びます。そのデザインフローを学びましょう。 - ユーザーの行動フローの可視化
UIの要件定義で整理した必要な情報を、ユーザーが実際に操作する形に落としましょう。「A画面で入力 → B画面で確認 → C画面で完了」などの遷移や画面同士の関係を”具体的に”洗い出し、問題点があれば早めに修正します。 - UIプロトタイプの作成
UIアイデアをラフにまず形にし、自分や他の人が触ってテストできる状態を作りましょう。要件を整理して得られた情報を元に、今の方向性で機能を満たせるのか?を具体的に検証しながらUIのクオリティ高めていくデザイン制作の流れを身につけましょう。
- プロトタイピング概念の理解
情報設計の基礎が身につけられるコンテンツ(例:書籍、オンラインコース)
- 書籍
「UIデザインの心理学」「誰のためのデザイン?」など、ユーザーの認知特性や情報整理の考え方を学べる書籍が役立ちます。 - オンラインコース
情報設計やUXライティングに特化したコースも活用しましょう。ワイヤーフレーム作成やユーザーフロー図の作成演習が含まれるものがおすすめです。 - ケーススタディを学ぶ
既存の有名なウェブサイトやアプリがどのように情報設計されているかを分析し、その裏側にある意図を推測してみましょう。
4-2-3. 【習得3】顧客理解と課題解決の基礎
顧客に価値を提供するデザインの基本を身につけよう UIデザインと聞くと、どうしても「画面づくり」や「操作性」に目が行きがちです。もちろん使いやすいUIは大切ですが、”使いやすい”はユーザーにとって価値のあるモノである前提のはずです。 ビジネスの現場では「顧客の課題を解決し、顧客にとって価値あるサービスを提供する」ことに向かってデザインを使ったりUIを作るという視点が何より重要です。
このパートでは、UIをただの“見た目”に終わらせないために、顧客のニーズや抱えている課題をしっかり捉え、それを解消する体験デザインへと落とし込む基礎を学んでいきます。非常に難易度の高いスキルで他のスキル同様に完璧に身につけることは求めません。 ただ“顧客が喜ぶサービス体験”を生み出すための顧客中心のデザインの考え方を一度体験することが重要です。 この基本を身につけて、顧客を理解して、課題解決をする素養を身につけることがこのパートのゴールになります。
- 体験デザインの基本:顧客の課題と価値の関係を理解し、UIを超えたサービス体験をデザインできるようになる。「なぜこのUIが必要なのか?」「そもそも顧客がなりたい状態は何か?」を整理し、自分のデザイン、UIが、”誰”の、”何のため”に存在するのかを理解しましょう。
- 顧客理解の基本:インタビューやリサーチを通じて、課題を具体的に把握し、解決策を提案するプロセスを体験する。UIのデザインそのものより、一歩上流の“顧客を理解する”プロセスが大事だと気づけるようになる。
- 顧客の課題を起点にしたサービスをデザインする:体験デザインと顧客理解の基本を論理で理解することはとても抽象度が高く難しいです。そのため、その基礎知識と進め方を使って、一度自分で課題を解決するようなサービスや機能をデザインしてみるのが有効です。
体験デザインと顧客理解で、課題解決の基礎を身につけよう
- 体験デザインの基本
- UXデザインの基本
UXデザイン=単なる使いやすさ、ではありません。UXデザインはかなり広く、Bonを例にすると3つに分解しています。「プロダクトのUX」、「顧客体験のUX」、「戦略のUX」この3つに分けています。単なる操作しやすいUXはプロダクトUXで情報設計までの基礎で考えるべきことです。ユーザーにとって良い体験を作るための「顧客体験のUX」についてこのパートでは学びます。 - ゴールダイレクテッドデザインの考え方
例えば「About Face」に紹介されるゴールダイレクテッドのフレームワークをもとに、顧客の抱える課題→価値→体験の関係性を学びましょう。何でもかんでも課題ではなく、ユーザーがなりたい状態にとって邪魔している優先度が高いものが”課題”になります。それを解決する体験を提供していくのがUIデザインの目的です。この関係性を顧客を軸に、体験価値として認識する基礎を身につけましょう。 - 実践形式で理解
自分のサービス想定を作り、顧客インタビューなどを通して価値を形にしていくフローを身につけましょう。
- UXデザインの基本
- 顧客価値と理解の基本
- 顧客を“知る”重要性
そもそもユーザー本人に質問をしなければ、本当の課題は見えてきません。基本的なインタビューの流れやヒアリングシートの作り方を学びましょう。 - 課題とは何か?
何を困りごとと捉えているのかを丁寧に引き出すことで、UIがどのように課題解決に寄与できるかを明確にします。 - ユーザーインタビューの基本
アンケートではなく対面でユーザーのことを知る重要性と、対面インタビューのやり方の基本を学び実践してみましょう。インタビューするべき内容の立て方、インタビューのやり方、まとめ方などをテンプレートの型を使って学習と実践することが可能です。
- 顧客を“知る”重要性
顧客理解と課題解決の基礎が身につけられるコンテンツ(例:書籍、オンラインコース、UXリサーチ関連資料)
- 書籍
「アバウトフェイス(About Face)」「ユーザーエクスペリエンスの要素」など、UXデザインの思考法やユーザー中心設計の考え方を学べる書籍を読みましょう。 - オンラインコース
UXリサーチ、ユーザーインタビュー、ペルソナ作成、カスタマージャーニーマップ作成といったテーマのコースを探しましょう。 - Webサイト・ブログ
UXデザインに関する専門ブログや企業のナレッジ共有記事を読み、具体的な事例から学びましょう。
次のステップ
習得した3つの基礎は「基本的なUI制作の流れ」になっています。つまりデザインツールからはじめ、この3つの基礎を身につけた状態で、はじめてUIをまとめにデザインする力を得られたことになります。このスキルを使って、次にポートフォリオに乗せるアウトプットを作成して行きましょう。
すでに基礎習得の中で作成したアウトプットがあるのであれば、時間がたった今見ると改善できる部分が見つかるでしょう。 今まで学んで身につけたスキルを使って採用でスキルを示すことができるポートフォリオ作成に移って行きましょう。
フェーズ3:ポートフォリオをつくろう
基礎スキルが伝わるポートフォリオを作成しよう 基礎理解をアウトプットに落とし込んで、デザイナーとしての強みを可視化! UI/UXを学んできたら、次に待っているのは「実際に何ができるのか?」を示すためのポートフォリオ作成です。これはあなたが持つスキルや思考プロセスを、採用担当者やクライアントに分かりやすく伝えるための必須ツール。 本フェーズでは、インターフェース基礎・情報設計・課題解決の3つの基礎を活かしたアウトプットを具体的に形にしていきます。同時に、ただ作品を並べるのではなく、「なぜそうデザインしたのか」「どんな意図や改善策を考えたのか」を簡潔に言語化する力も身につけるのがポイントです。
このフェーズで目指す状態
- 最低3つのアウトプットを完成させる
アウトプットが少ないと再現性が分かりづらいため、最低3つのアウトプットを目指しましょう。複数の例があることで、あなたの思考パターンや強みがよりハッキリ見えます。また、その思考プロセスも言語化してデザインを説明する力やデザインの理解を示しましょう。 - 「どんな人物なのか」が伝わる
スキルだけでなく、経歴・学習スタンス・チームで働くときの姿勢などもポートフォリオで表現しましょう。採用する側はスキルが高いだけではなく一緒に仕事ができるかなどの要素も評価の対象となります。
ポートフォリオに載せるべき必須項目
アウトプット(各プロジェクトで以下の要素を盛り込む)
- プロジェクトの概要と担当範囲
どのような課題を解決しようとしたのか、どんなサービスなのか、あなたがどの部分を担当したのかを明確に。 - インターフェース基礎スキルの作品
配色やボタン配置、レイアウトなど、基本的なUIの見せ方が分かるもの。実際にFigmaで作成した画面デザイン。 - 情報設計基礎スキルの作品
ワイヤーフレーム、サイトマップ、ユーザーフロー図、情報アーキテクチャ図など、情報整理と設計のプロセスがわかる資料。 - 顧客理解&課題解決のスキルの作品
ユーザーリサーチのプロセス(インタビュー内容、ペルソナ、カスタマージャーニーマップなど)、発見した課題、それに対するUI/UXでの改善提案、Before/Afterの比較など。なぜそのデザインにしたのか、どのような効果を期待したのかを論理的に説明しましょう。 - 使用ツールと役割
Figma, Adobe XD, Miro, Lucidchart などの使用ツールと、プロジェクトにおけるあなたの役割を明記。 - 学びと今後の展望
プロジェクトを通して何を学び、今後どのようにスキルアップしていきたいかを記述。
自分自身の紹介
- 経歴や学習の背景
どんな環境で、どのようにデザインを学んできたのか。今までのキャリアはどういう特徴があるのか。未経験からの挑戦であれば、その熱意と学習プロセスを具体的に。 - デザインへの考え方
「なぜデザインが好きなのか」「どんな分野に興味があるのか」「どういうデザインをしていきたいのか」などをブログやポートフォリオ上でまとめましょう。 - 成長意欲が伝わるエピソード
失敗や挫折をどう乗り越えたかなど、ポテンシャルを示すエピソードがあると印象的です。
「UI/UXポートフォリオ作成」に役立つコンテンツ(例:Webサイト、書籍)
- ポートフォリオ事例サイト
他のUI/UXデザイナーのポートフォリオを見て、構成や表現方法を参考にしましょう。「UI/UX ポートフォリオ 事例」などで検索すると多くの参考例が見つかります。 - ポートフォリオ作成に関するWeb記事や書籍
「デザイナーのポートフォリオの作り方」といったテーマで解説している記事や書籍を参考に、戦略的にポートフォリオを構築しましょう。 - フィードバックの機会
可能であれば、現役デザイナーやメンターにポートフォリオを見てもらい、客観的なフィードバックをもらいましょう。
次のステップ
ポートフォリオの内容が固まったら、いよいよクライアント獲得・仕事探しのフェーズに進みましょう。ポートフォリオ自体はいつまででもクオリティを高めるために時間を使えますが、応募しないと仕事は獲得できません。自分で締め切りを作り、その範囲でクオリティUPにフォーカスして、次のフェーズに進みましょう。
フェーズ4:クライアント獲得・仕事探し
ポートフォリオが完成したら、いよいよ仕事獲得に向けた活動を開始します。特にフリーランスの場合、仕事は向こうから降ってくるものではありません。能動的に動くことが不可欠です。
4-4-1. 最低30社以上への応募・アプローチを視野に入れよう
未経験からUI/UXデザイナーとして仕事を見つけるのは、簡単なことではありません。特に「未経験歓迎」と明示している案件は実際にはかなり限られています。
- 未経験枠が公開されているのは少ない
知名度の高い企業はスキルのある中途デザイナーが自然と集まるため、未経験枠を設ける必要性が薄いです。デザイナー採用に苦戦している企業も、あえて”未経験”と出すとレベルの高い人が応募しづらいと考えることもあります。そのため、未経験を表で表示していない企業にも積極的に応募することで、実は募集している可能性を確認する必要があります。 - 会社の状況やタイミング次第
デザイナー枠が埋まってしまうと募集を打ち切るケースも多々あります。内情は外からは見えづらく、こちらから探るのも難しいものです。 - マッチする企業は意外と少ない
認知度の低い企業ほどデザイナーの採用に苦戦しがちで、未経験でも育てたいと思ってくれる確率が高い傾向にあります。しかし、そのような企業を自力で探し当てるにはある程度の件数に当たる必要があります。 - 数をこなすことの重要性
企業ごとに求めるスキルや強みは異なるため、母数を増やすことで“タイミングや方向性”の合う企業に出会いやすくなります。特に未経験の場合は“まず話を聞いてもらう”ハードルが高いため、数をこなすことでチャンスを見つけましょう。フリーランスの場合、案件の単価や期間も様々なので、複数の案件に応募して自分に合ったものを見つけるのが一般的です。
4-4-2. 入りたい会社・見つけたい案件を探して分析しよう
とりあえず応募数が必要とはいえ、「どんな会社でもいいので雇ってください…」というスタンスだと魅力は半減しますよね。恋愛にたとえるなら誰でもいいという人は、なかなか選ばれないのと同じです。なので自分で入りたい会社、自分の経験や興味と相性の良さそうな会社などを調べて、能動的にアプローチすることは必須です。
- 興味のある企業・案件をリストアップ
まずは自分が“興味を持てる会社や案件をリストアップしましょう。「自分の好きな領域」「自分がやりたいサービス」「デザインに対して理解がある会社」など、興味のある企業を探す作業は大事です。 - 企業リサーチに役立つサービス
以下のようなサービスなどを使ってデジタルな会社でデザイナーを求めている会社を探しましょう。- Wantedly
ベンチャーやスタートアップの採用情報が多く集まり、UI/UXデザイナー枠で検索しやすいです。企業のカルチャーやメンバーの雰囲気を知るのにも便利です。 - Lancers / CrowdWorks
国内最大級のフリーランス向けクラウドソーシングサイトです。UI/UXデザインやWebデザインの案件が多数掲載されており、実績作りのための案件探しにも役立ちます。 - Workship / 複業クラウド / クラウドテック
IT・Web業界に特化した日本のフリーランスマッチングサービスです。専門職に特化しているため、質の高い案件が見つかりやすいでしょう。 - note / 個人ブログ
企業の社員が発信していることも多く、現場のリアルな声が見つかります。「会社名+デザイナー」で検索してみると、新たな気づきがあるかもしれません。 - デザインコミュニティ
SNS上のデザインコミュニティや、オフラインのミートアップに参加するのも有効です。非公開案件や人脈形成につながる可能性があります。
- Wantedly
- 応募する際のポイント
- 企業がどんな強みを求めているかを把握
サービス内容や社風を理解したうえで、「自分のデザイン観がどう役に立つか」を明確にアピールする。 - 自分のやりたいことを明確にする
「この会社で○○を学びたい」「このサービスに共感している」など、企業側に刺さる動機づけを伝えることで、採用の可能性が高まります。 - ポートフォリオとの連携
提出するポートフォリオは、応募先の企業や案件に合わせてカスタマイズし、特にアピールしたいスキルやプロジェクトが目立つように工夫しましょう。
- 企業がどんな強みを求めているかを把握
次のステップ:実際の面接や応募準備へ
- ポートフォリオと志望動機をしっかりリンクさせる
「なぜこのUIを作ったのか?」など、ポートフォリオに込めた想いや学習プロセスを自信を持って説明できるようにしましょう。 - 企業分析に時間をかけすぎない
応募先が定まらないままダラダラとリサーチを続けるのはNGです。ある程度のリストができたら、期限を区切って応募しはじめることも大切です。 - 継続的な学習と改善
応募や面接で得られたフィードバックを元に、ポートフォリオやスキルを継続的に改善していく姿勢が重要です。
5. まとめ:継続的な学習とスキルアップへ
この記事では、未経験からフリーランスUI/UXデザイナーに転職するためのロードマップを解説してきました。時間はかかりますが、やれば確実にスキルは身につきます。才能は必要ありません。必要な基礎ロジックを知ってそれを真似してひたすら練習するのみです。ぜひトライしてみてください。
最後にこの記事のまとめを貼っておきます。
- 未経験からUI/UXデザイナーを目指す全体像を把握する
はじめに、UI/UXを学ぶ上でのゴールイメージを持ち、デザインの基礎から仕事獲得までの道のりを俯瞰しておきましょう。 - まずはFigmaなどデザインツールの操作を身につける
手を動かしながらUIを実際に作る経験が、今後のUI/UX理論を学ぶ際の土台になります。 - デザイン原則や“ふつうのUI”を真似して基礎を固める
色や余白、タイポグラフィなどの基本や、既存のUIをトレースすることで、短期間でデザインの引き出しを増やしましょう。 - UI/UXを理解する3つの基礎を押さえる
「インターフェース基礎」「情報設計」「顧客理解と課題解決」の3点を順番に学び、実務に役立つ基礎体力をつけます。 - インターフェース設計で“使いやすさ”を具体化する
ボタン配置や画面遷移、状態変化などを考慮し、人が迷わず操作できるUIを設計する力を養いましょう。 - 要件をUIへ落とし込む“情報設計”を身につける
ユーザーがどんな流れで機能を利用するのか?を整理し、使いやすいUIに仕上げるための論理的なプロセスを学ぶのがポイントです。 - 「顧客理解」を起点にサービス価値を高める
どんな人が、何に困っているのか?を把握し、それをUIや体験設計に落とし込むことで“課題解決につながるデザイン”を目指します。 - ポートフォリオ作成でアウトプットを形にする
学んだスキルをまとめ、なぜそのデザインが必要なのかを説明できるように整理します。最低3つの事例を示して再現性をアピールしましょう。 - 仕事獲得では複数へのアプローチとリサーチが必須
未経験からの採用枠は限られるため、数を打ちながら入りたい企業や案件も入念に調べ、相性の良いものを狙いましょう。クラウドソーシングやフリーランス向けマッチングサイトも活用します。 - 継続的な学習とスキルアップ
UI/UXデザインの分野は常に進化しています。常に新しい情報を取り入れ、スキルを磨き続けることが、フリーランスとして長く活躍するための鍵となります。
このロードマップを参考に、あなたのフリーランスUI/UXデザイナーへの道を切り開いてください。応援しています!