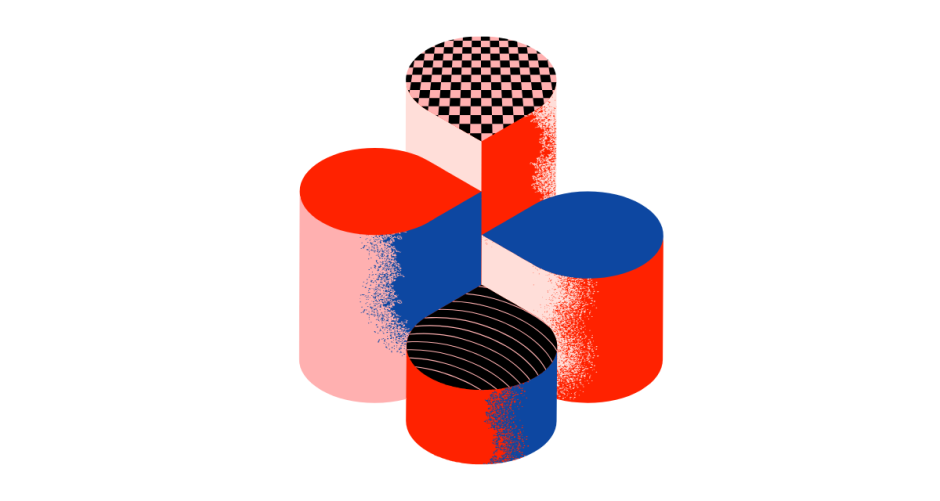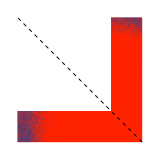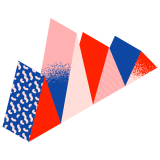フリーランスとして独立し、事業が成長する中で「法人化」という選択肢が頭をよぎることは、多くの方が経験することでしょう。僕自身もまさにそうでした。年商や利益が伸びてきたとき、「このまま個人事業でいいのかな?」「法人にした方が節税になるって本当?」といった疑問にぶつかりました。
そして、年商1,000万円という節目で法人化を決断。結果として、「もっと早くやっておけばよかった!」と思えるほど、法人化によって得られた恩恵は大きかったと感じています。
とはいえ、法人化は決してゴールではなく、あくまで「次のステージへの手段」です。なんとなく節税のためだけに法人化してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。
この記事では、僕自身の法人化経験に基づき、フリーランスから法人化を検討すべきタイミングから、具体的な手続き、そして法人化のメリット・デメリットまで、リアルな視点から網羅的に解説します。さらに、会計ソフトや銀行口座、登記住所など、現代のフリーランスに役立つツールやサービスもたっぷり紹介しますね。
フリーランスとしてもう一段ステップアップしたいと考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
なぜ法人化を検討すべきなのか?
個人事業主としてある程度の売上や実績が出てくると、「法人化」という言葉が自然と視野に入ってきます。ここでは、なぜフリーランスが法人化を検討すべきなのか、3つの主要な観点から整理していきます。
信用力が上がる
まず最も実感しやすいのが、「取引先からの信用」です。法人というだけで大手企業や金融機関からの見え方が大きく変わります。
実際、僕も個人事業主として活動していたときは、大企業との取引で「個人名義の契約は難しいです」と断られることがありました。しかし、法人化してからは法人名義での契約がスムーズになり、クレジットカードや口座開設、リース契約なども簡単に通るようになったんです。
また、今後人を雇いたい、あるいは外注パートナーを増やしてチームで動きたいという場合でも、法人の方が採用面や委託契約の信頼性が高まります。
節税メリットがある
法人化の最大の動機として語られるのが、「節税メリット」ですよね。個人事業では所得税が累進課税(最大45%)ですが、法人税は一定率(中小企業なら約23.2%)です。利益がある程度出てくると、法人にすることで手元に残るお金が増える可能性が高まります。
加えて、法人から役員報酬として自分の給与を支給すれば、給与所得控除が使えるようになり、さらに税金を軽減できます。その他にも、以下のような節税手段が可能です。
- 家族への給与支払い(所得分散): 家族を役員や従業員として報酬を支払うことで、世帯全体の所得を分散させ、税負担を軽減できます。
- 退職金制度の設計: 法人として退職金制度を設けることで、将来の生活資金を準備しつつ、法人税の課税所得を減らせます。
- 経費の範囲の拡大: 個人事業では認められにくい生命保険料や出張手当なども、法人の経費として計上できる場合があります。
- 消費税の免税期間: 法人設立後、資本金が1,000万円未満であれば、最長2年間は消費税の納税義務が免除されます(特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合を除く)。これは地味に大きなメリットです。
- 繰越欠損金の控除期間: 法人が赤字になった場合、その欠損金を翌期以降の利益と相殺できる「繰越欠損金」の制度があります。個人事業主の場合、青色申告で3年間ですが、法人の場合は10年間(平成30年4月1日以降開始事業年度)繰り越すことができます。
ただし、節税ばかりを目的にして法人化すると、かえって税務リスクが増すこともあります。あくまで「実態に見合った設計」が必要です。
社会保険への切り替え
個人事業主は原則「国民健康保険・国民年金」に加入しますが、法人化すると原則「健康保険・厚生年金」に切り替わります。
一見すると「社会保険は高いから損」と思うかもしれませんが、実は長期的にはメリットも多いんです。たとえば:
- 将来もらえる年金額が増える: 厚生年金に加入することで、将来受け取れる年金額が国民年金のみの場合よりも増える可能性が高いです。
- 高額医療費制度の上限が低くなる: 健康保険に加入することで、医療費が高額になった場合の上限額が国民健康保険よりも低く設定されることがあります。
- 家族を扶養に入れやすくなる: 配偶者や子どもがいる場合、一定の条件を満たせば扶養に入れることができ、家族の健康保険料の負担を軽減できます。
- 保険料の半分を会社が負担: 社会保険料の半分は会社が負担するため、個人事業主時代に全額自己負担だった国民健康保険・国民年金と比較すると、個人負担が実質的に軽減されることになります。
社会保険は今すぐの節約にはなりませんが、未来の安心として非常に重要なポイントです。特に家族がいる方、将来の備えを考えたい方には検討すべき要素ですよ。
売上いくらで法人化すべきか?
「いつ法人化すればいいのか?」というのは、誰もが迷うテーマです。特に初めてのフリーランスにとっては、「売上のどのラインで法人化すべきか?」という明確な基準がないのが悩みの種ですよね。
目安は売上1,000万円超?それとも利益ベース?
よく「売上1,000万円を超えたら法人化した方がいい」と言われますが、これは「消費税の課税事業者になるライン」と混同されがちです。
実際は、「利益がどれくらい出ているか」の方が法人化の判断材料になります。たとえば、売上が2,000万円でも経費が多くて利益が少なければ、法人にするメリットはあまりありません。
「利益ベースで年間500万〜700万円を超えるなら検討ライン」とされます。これは、このあたりの所得から個人の所得税率が法人税率を上回るケースが多くなるためです。
月収ベース・年間利益から判断するロジック
もっと直感的に言うと、月収(税引き前利益)が40〜60万円以上を安定して出せるようになったら、法人化を視野に入れるのが自然です。
理由は、所得税の累進課税(33%・43%など)に突入し始めるゾーンに入るからです。節税のインパクトも大きくなります。
僕の実例:年商1,250万・利益400万で法人化した理由
僕自身の場合、フリーランス2年目が終わった頃に年商1,250万円、経費を引いた利益で400万円ほどに達しました。この時点で以下のような悩みが出てきたんです。
- 所得税・住民税がバカにならない
- 銀行やクレカの審査が通りにくい
- 消費税の免税期間が終わる
そのタイミングで、信頼している税理士にも相談し「今法人化しても十分元が取れる」と背中を押され、法人設立を決意しました。
結果として、税金のコントロールがしやすくなり、社会的信用も上がり、営業や交渉もしやすくなったと実感しています。
法人化のタイミングでよくある失敗と注意点
法人化は節税や信用力アップといった大きなメリットがある一方、タイミングや準備を誤ると「想定外の負担」や「後悔」につながることもあるのが現実です。ここでは、実際によくある失敗例と、避けるための注意点を紹介します。
「節税目的だけ」で焦って法人化する
もっともよくあるのが、「節税になるらしいから…」という理由だけで法人化してしまうケース。確かに、一定の利益がある場合には税率をコントロールできるメリットはありますが、それはあくまで全体の設計が整ってこそです。
法人になると、たとえ赤字であっても最低7万円の法人住民税(均等割)が毎年かかります。さらに、社会保険の強制加入や、顧問税理士費用、会計ソフトの法人プランなど、固定費が数万円単位で増えるのが現実です。
つまり、「利益がそれほど出ていない段階」で法人化すると、かえって負担が増え、手元に残るキャッシュが減ってしまうのです。
開業届から1年も経っていない段階で法人化する
個人事業主としての実績がほとんどない状態でいきなり法人を設立すると、下記のような“信用不足”に直面することがあります。
- 銀行口座や法人クレジットカードの審査が通らない
- 補助金や融資で「実績不足」と判断される
- 開業したばかりで顧問税理士や社労士が見つからない
実際には、まずは個人事業として1〜2年しっかりと実績を作ることで、法人化後のスタートがスムーズになりますよ。
経費や売上の分離ができていない
法人と個人の口座・お金の流れがごちゃごちゃなまま法人化すると、会計処理が複雑になり、税務調査のリスクも高まります。特に注意すべきは、下記のような点です。
- 個人名義のクレジットカードをそのまま業務に使う
- 家族への報酬支払いが不明確
- 法人の売上を個人口座で受け取ってしまう
これらは「仮装隠蔽」と見なされるリスクもあるため、法人化前後のタイミングでは口座・クレカ・会計処理の整理が必須です。
「法人成り」の準備を怠るとトラブルになる
法人化する際、既存のクライアントとの契約をどう移行するか、前もって合意しておく必要があります。法人として新たに契約を結ぶ場合、以下のような確認が必要です。
- 「業務委託先を法人に変えてもOKか?」
- 「契約書は法人名義に切り替える必要があるか?」
- 「請求書の宛名や支払い方法は変わるか?」
このように、法人化によって発生する契約・事務の変更作業も意外と時間と手間がかかるポイントです。
対策:法人化の前に最低限やっておくべきこと
- 利益500万円以上を安定して出せる見込みがあるか確認する。
- 売上・経費の仕訳を会計ソフトできちんと整理しておく。
- 税理士や社労士に早めに相談し、法人設立のタイミングを見極める。
- 口座・クレカ・契約の整理をしておく。
- クライアントとの契約変更に関する確認を取る。
これらを押さえておくことで、法人化後のトラブルや後悔は大幅に減らせますよ。
法人化の手続きステップをわかりやすく解説
法人化と聞くと、「なんだか難しそう」「法務局とか行くの面倒そう」と感じる人も多いでしょう。でも実際は、ステップを分解すれば誰でもできるプロセスです。
ここでは、フリーランスが法人を立ち上げる際に必要なステップを、できる限りシンプルに分解して解説します。
Step1:定款の作成と認証
法人設立の第一歩は「定款(ていかん)の作成」です。定款とは、会社のルールや事業目的を記載した“会社の憲法”のようなもの。
- 会社名(商号)
- 事業内容
- 本店所在地
- 役員構成
- 発行株式の数や出資額
などを記載し、これを公証役場で認証してもらいます。現在は電子定款が主流で、印紙代4万円をカットできるのがメリットです。
僕も使ったのですが、マネーフォワード 会社設立がおすすめです。定款の作成・電子申請・印紙代の節約まで一気通貫で支援してくれますよ。
Step2:登記申請(法務局)
定款が認証されたら、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。これにより正式に法人(株式会社や合同会社など)が誕生します。
必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 登記すべき事項を記載した用紙
- 役員の就任承諾書
- 印鑑証明書(発起人・役員全員分)
- 資本金の払い込みを証明する書類
- 印鑑届書(会社の実印を登録するため)
- その他、必要に応じて添付書類
提出後、約1〜2週間で登記が完了します。
Step3:税務署・年金事務所などへの届出
登記完了後、以下の機関への届け出が必要です。
- 【税務署】 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
- 【都道府県・市町村】 事業開始届出
- 【年金事務所】 新規適用届、被保険者資格取得届など(社会保険加入のため)
- 【労働基準監督署・ハローワーク】 労働保険関係の届出(従業員を雇用する場合)
これらはネットや郵送でも対応可能ですが、税理士さんに任せるのがスムーズです。
Step4:社会保険の加入手続き
法人になると、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。加入は登記日から2週間以内が目安です。
「社会保険料が高い」と感じるかもしれませんが、これは未来の安心への先行投資と捉えるべきものです。
Step5:法人用会計ソフト・口座・登記住所の整備
法人運営では「法人用の経理環境」が不可欠です。以下を早めに整えておきましょう。
- 法人口座(住信SBIネット銀行/GMOあおぞらネット銀行がおすすめ)
- 会計ソフト(マネーフォワード クラウド会計)
- 登記住所(自宅がNGな場合はバーチャルオフィス「NAWABARI」が便利)
これらをきちんと整備することで、法人運営の事務作業や税務対応が格段に楽になりますよ。
これ使えば簡単!法人設立に便利なサービス
法人化にはさまざまな手続きが伴いますが、今の時代はツールやオンラインサービスを使えば、大半の作業が一人で完結できます。
ここでは、実際に使って便利だった、または法人化のサポートに最適なサービスを厳選して紹介します。
会計ソフトは「マネーフォワード クラウド会計」が神!
法人を設立したら、会計の仕組みをゼロから構築する必要があります。個人事業主時代に「確定申告ソフト」を使っていた方も、法人会計は少しルールが異なります。
そこでおすすめなのが、マネーフォワード 会社設立です。
法人利用でおすすめな理由
- 法人の複式簿記に完全対応(仕訳も自動でラク!)
- 銀行・クレカ・レジなどと自動連携できる
- 税理士との共有も超スムーズ
- 決算書も簡単に出力できる
個人事業で「マネーフォワード ME」や「クラウド確定申告」に慣れている方は、そのままスライドできるのもメリット。
僕自身も、法人化後すぐに導入しましたが、「なんでもっと早くやってなかったんだ…」と思うくらい楽になりましたね。
登記住所は「バーチャルオフィス」で十分。コスパ重視なら「NAWABARI」
法人設立には登記住所(本店所在地)の登録が必要です。自宅でも登記は可能ですが、次のような理由で避けたい人も多いはず。
- 名刺やウェブサイトに自宅住所を載せたくない
- 郵便物が仕事とプライベートで混ざるのが嫌
- 家族に法人の郵便物が届くのが気まずい
そんなときに便利なのが、バーチャルオフィスです。
とくに「NAWABARI(ナワバリ)」は、月額1,650円〜という安さで法人登記OK、郵送転送付きという圧倒的なコスパ。東京都内の一等地住所も選べるので、見た目の印象もアップしますよ。
法人口座は「住信SBIネット銀行」か「GMOあおぞらネット銀行」
法人化後は、個人口座と完全に分けて法人用の銀行口座を作る必要があります。
昔ながらのメガバンクは「法人開設に2週間以上かかる」「手数料が高い」「オンライン管理が面倒」といった課題が多く、僕は最初からネット銀行を選びました。
おすすめは以下の2社です。
- 開設が早い(オンラインで完結)
- 振込手数料が安い
- スマホアプリの使い勝手が良い
- freee・マネフォとの連携も◎
- 預金金利が高め
- バーチャル口座が複数作れる
- API連携が強力(SaaSとの親和性高)
「複数サービスと連携して効率化したい」「外注や取引先が多い」という方は、GMOも良い選択肢です。
法人化のデメリットとリスク
法人化は魅力的な選択肢ですが、当然ながら「良いことづくめ」ではありません。
特にフリーランスが初めて法人を運営する際には、思わぬ落とし穴に注意が必要です。ここでは、法人化によるデメリットとリスクをリアルに解説します。
赤字でも税金がかかる(法人住民税・均等割)
法人になると、たとえ売上がゼロでも「法人住民税(均等割)」という税金が必ず発生します。
その金額は、年間最低でも約7万円(東京都なら約7万1,000円)。
利益が出ていなくても、「会社を維持するコスト」がかかるという点は、個人事業と大きく異なる部分です。
社会保険料が高くなる可能性がある
法人になると、代表者=役員にも強制的に「社会保険(厚生年金+健康保険)」が適用されます。
これは、国民健康保険+国民年金に比べると、毎月の支払いが高くなるケースが多いです。 たとえば、月額報酬を30万円と設定した場合、社会保険料は月に約5〜6万円(法人・個人で折半)となります。
利益が少ない状態で法人化してしまうと、保険料の負担が重くのしかかってしまうため要注意です。
経理や事務手続きが複雑になる
法人会計は「複式簿記」が必須で、個人事業主よりも提出書類や会計処理が圧倒的に増えます。
- 役員報酬の設定と変更
- 源泉徴収の対応
- 年末調整や法定調書
- 決算書の作成と税務申告
など、慣れないうちはプロの手を借りることがほぼ必須です。
税理士との顧問契約(年間10万円〜30万円ほど)も実質的な固定コストとなります。
法人をたたむ(解散・清算)ときの手続きが大変
事業がうまくいかなくなった場合、法人の廃業は個人事業と比べて非常に面倒です。
- 株主総会の開催
- 清算人の選任
- 清算結了登記
- 税務署への書類提出
など、複雑な手続きを踏まなければなりません。「一度作った法人は簡単には消せない」という覚悟も必要です。
法人化すべき人・しなくていい人
法人化を「すべきかどうか」の判断は、売上や利益だけではなく、ライフスタイル・事業の将来像・リスク許容度など複数の要素が関わります。
ここでは、法人化が向いている人・そうでない人を、具体例を交えながら整理します。
法人化すべき人の特徴
利益が安定して出ている(目安:年間500万円以上) 税制的なメリットを最大限に活かすためには、やはり利益が一定水準を超えていることが前提条件です。
今後スタッフを雇う/チーム化を目指している 人を雇う予定があるなら、法人の方が雇用契約・社会保険・採用広報などがスムーズになります。
クライアントが大企業や官公庁など「法人との契約」を求めてくる 取引先によっては「法人格がないと取引できない」ことも珍しくありません。
補助金・助成金・融資を活用したい人 法人格を持っている方が、創業支援やIT導入補助金、信用保証付き融資などにアクセスしやすくなります。
法人化しないほうが良い人の特徴
売上が不安定・開業して間もない 安定的な利益が出ていない段階では、法人化のメリットよりも固定コストの負担が大きくなる可能性があります。
一人で完結するビジネスを淡々と継続する予定 ライター・デザイナー・講師など「ひとり社業」を割り切って続ける場合は、個人事業でも十分に成立します。
会計や事務作業に手間をかけたくない人 法人化すれば、やるべき事務タスクは確実に増えます。「経理は全部自分でやりたい」という人にはストレスが大きいかもしれません。
「法人化の判断」は自分の事業フェーズと向き合うきっかけになる
法人化すべきかどうかを考えるプロセスは、単なる手続きの検討ではなく、
- どんな未来を描いているか?
- 売上やチームの拡大を見込んでいるか?
- どこまでリスクを取れるのか?
といった事業と人生を再設計する良い機会になります。
実際に僕も、法人化を検討したタイミングで、経費・保険・契約・採用・資金調達などあらゆる面を見直しました。その経験があったからこそ、法人化後のスタートダッシュがスムーズになったと感じています。
法人化後に受けられる補助金・助成金って?
フリーランスから法人化すると、実は見逃せないのが「補助金・助成金」の存在です。個人事業主では対象外でも、法人格を持つことで国や自治体からのサポートにアクセスしやすくなるという利点があります。
ここでは、法人化後に活用できる主な支援制度をいくつか紹介します。
創業支援系:創業助成金(東京都・自治体)
東京都など一部の自治体では、法人設立後の事業立ち上げに対して「創業助成金」が用意されています。
たとえば東京都の「創業助成事業」では、最大300万円(助成率2/3)の補助が受けられます。対象となる経費は次のようなものです。
- 人件費(アルバイト・社員)
- 広告宣伝費(LP制作、広告運用)
- 外注費(デザイナー、エンジニア)
- 事務所賃料
注意点として、法人設立直後に申し込んでも間に合わないことが多く、申請前に説明会への参加や計画書の提出が必要なので、早めに調査しておくのがおすすめです。
中小企業庁:IT導入補助金・事業再構築補助金など
法人化したてでも、中小企業向けの補助金制度は多数あります。 特に注目なのが以下の2つです。
IT導入補助金(最大450万円)
自社の業務効率化を目的としたITツール導入費用の一部を補助する制度。たとえば、
- MAツール、CRM導入
- オンライン予約システム
- 会計・勤怠・請求などのSaaS導入
などが対象になります。フリーランス時代には手が届かなかったサービスを導入するチャンスです。
事業再構築補助金(最大8,000万円)
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編など、思い切った事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する大型補助金。ハードルは高いですが、新しい収益モデルを試したい法人にとってはチャンスです。
金融系:日本政策金融公庫・信用保証協会の融資
法人化により、「公的融資」の選択肢も広がります。
- 日本政策金融公庫の創業融資(無担保・無保証可)
- 各自治体の制度融資(利子補給あり)
これらは、事業計画がしっかりしていれば、設立直後でも資金調達できることが魅力です。特に設備投資や広告費、採用コストが必要なときには強い味方になりますよ。
社会保険関連の助成金も要チェック
法人が従業員を雇用する場合、雇用系の助成金も対象になります。
- キャリアアップ助成金(非正規社員を正社員化で最大72万円)
- 人材開発支援助成金(従業員の研修費の補助)
- 両立支援等助成金(育児・介護と仕事の両立支援)
「人を育てたい」「小さく採用を始めたい」法人にとっては、費用面での後押しになる制度です。
申請には事前準備が不可欠
補助金や助成金は「出せばもらえる」ものではありません。多くの場合、
- 申請前の説明会参加
- 事業計画書の提出
- 会計帳簿の整備
- 規定に基づいた帳票管理
などが求められます。法人設立後は、早めに会計・記帳の体制を整え、補助金に強い税理士と連携することが鍵になります。
まとめ|法人化は「未来への投資」。自分に合った選択を
フリーランスから法人化を考えるタイミングは、事業が一段階成長し、「もっと大きな可能性」を追いたくなったときだと思います。
- 売上が安定してきた
- 節税が気になってきた
- 信用力や社会保険の見直しをしたい
- チーム化や採用を視野に入れている
- 補助金や融資で事業拡大を狙いたい
これらのどれかにピンとくる人は、法人化が現実的な選択肢になってきているはずです。
実体験から言えること:法人化は「手間」だけど、やってよかった
僕自身も、年商1,000万円を超えた段階で法人化を決断しました。
確かに最初は書類や手続きに戸惑うことも多かったですが、マネーフォワードや住信SBIなどのツールを活用して、スムーズに体制を整えることができました。
その結果、
- 税金のコントロールが可能に
- 信用力が増して大手企業と契約が進みやすく
- 社会保険や資金繰りへの見通しが立てやすくなった
など、「思ったより得るものが多かった」と実感しています。
とはいえ「法人化すれば成功する」というわけではない
大事なのは、「自分の働き方と将来設計に合っているか」を見極めることです。
無理に法人化してしまうと、固定コストに圧迫されて苦しくなるケースもあります。
- 今はまだフリーランスとして地盤を固めるフェーズかもしれない
- 一人で自由にやる方が幸せかもしれない
- 節税以上に、やりたいことの実現に注力すべき時期かもしれない
そんな「立ち止まって考える視点」を持つこともまた、プロフェッショナルとして大事な力です。
最後に:こんな人はぜひ法人化を検討してみてほしい
- 売上が年間1,000万円を超えてきた
- 利益が安定して出るようになった
- 社会保険の手当てや信用力を整えたい
- 今後チームを作りたい、投資を受けたい
- スモールスタートでしっかりと法人経営を学びたい
上記に当てはまる方は、まずは「法人化について調べてみる」「税理士に相談してみる」だけでもOKです。
法人化は、あなたの働き方を広げ、未来を変える一歩になり得ます。
焦らず、でも一歩ずつ、未来を見据えて選択していきましょう。