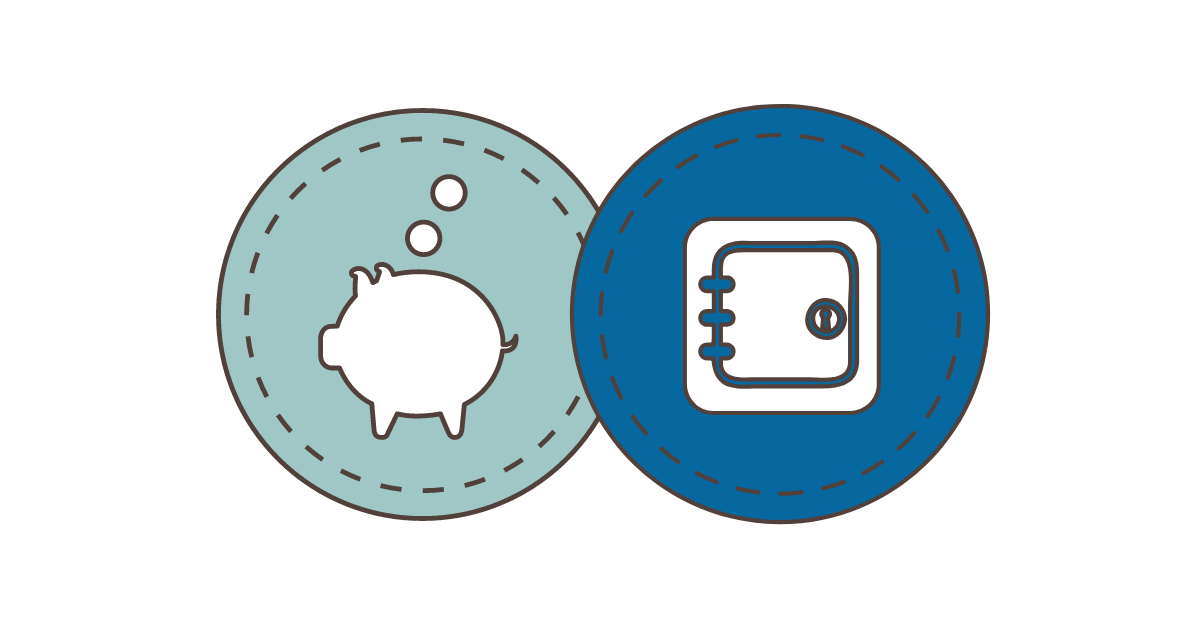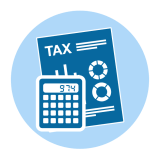確定申告で最も手間なことは税金の計算です。経費を増やして所得を減らしたり、青色申告で特別控除枠を受け取ったりなど、知っておくと得する節税方法があります。
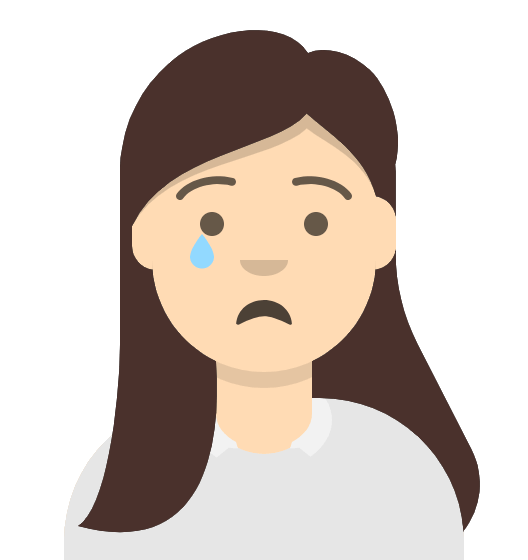
実はそんなに税金支払わなくてよかったの?!
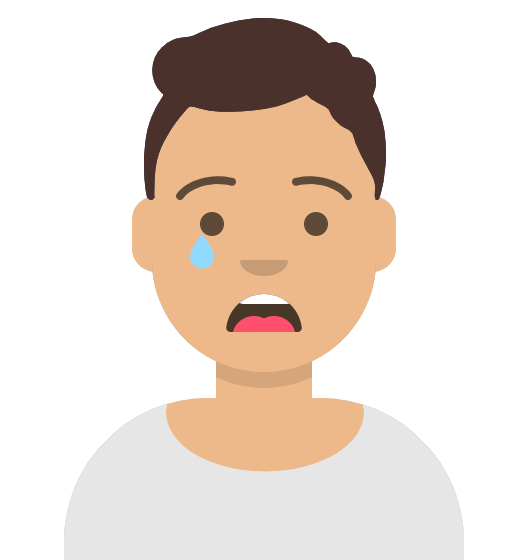
そんなに払う必要があったの?!知らなかった!
と、なる前に本稿では、所得税と住民税の税率の基礎や計算方法について説明します。
また、個人的に調べて疑問に思ったことは、現役のベテラン個人事業主の方に答えてもらいましたので、そちらも合わせてご覧ください。
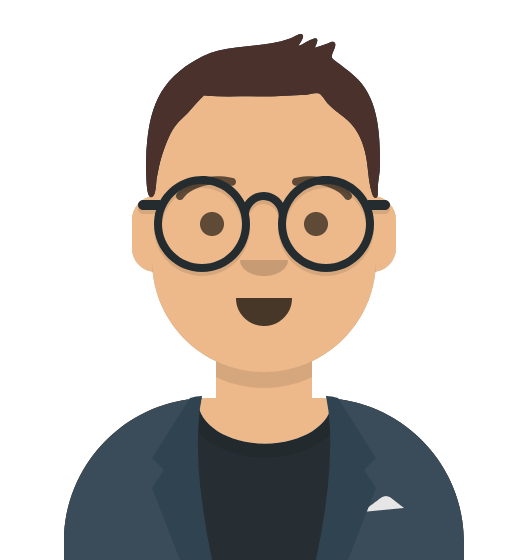
なんでもどうぞ!
個人事業における所得税について
所得税の基本について
所得税は毎年1月1日から12月31日までの期間を1つの計算期間とし、その間に利益がでた金額に対して税額が計算されます。
日本では所得が高くなればなるほど段階的に税率が高くなる『超過累進課税方式』が採用されています。
この超過累進課税方式が採用されていることにより、支払う所得税が違う事例を紹介します。
同じ利益を出して税率が違うケースを見てみる
例えば、1千万円利益をあげていたAさんとBさんがいたとします。
![]() Aさん
Aさん
1年間に1千万円の利益を出しましたが、その後4年間は利益が出ませんでした。
![]() Bさん
Bさん
毎年200万円ずつを5年間にかけて利益を出しました。
この時のAさんとBさんの税負担はどうなるでしょうか?
所得税は1月1日から12月31日までの1年間単位で計算します。所得税の速算表にあてはめて計算してみましょう。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5.0% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10.0% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20.0% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23.0% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33.0% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40.0% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45.0% | 4,796,000円 |
![]() Aさん
Aさん
1年目に1千万円だったので、
1,000万円×33%-153.6万円=176.4万円
その後4年間は税額0円
Aさんの場合は、初年度に税金を払ったため、その後は利益がないので税金は発生しませんでした。
![]() Bさん
Bさん
毎年200万円ずつの利益なので、
200万円×10%-9.75万円=10.25万円
5年間で10.25万円×5年間=51.25万円
一方Bさんは毎年少しずつ税金を払うことになります。
ご覧の通りなんとその差額5年間で約125万円にもなります。
合計では同じ金額の利益ですが、1年間に一気に利益を出したAさんの方が、毎年少しずつ利益を出したBさんに比べて税負担が大きくなりました。
そんなAさんのような方に、朗報とも言える税制度がありますので紹介しておきます。
平均課税制度による緩和策を知る!
『平均課税制度』は、先ほどの例のように特定の年だけ所得が大きくなる場合に、税負担の不公平さを緩和させるための制度です。
平均課税制度は『5分5乗方式』といわれ、その名の通り所得を5分割した金額に対して税率を掛け、その金額を5倍して税額を計算する方法です。
先ほどのAさんの例で平均課税制度を適用すると、1年目は下記のような計算式になります。
- 1,000万円÷5=200万円(5分)200万円×10%-9.75万円=10.25万円
- 10.25万円×5=51.255万円
Aさんは1年目に1,000万円を利益を出し、それに対する税額が51.25万円となりました。
2年目以降は当然税額は無しですから5年間の総合で、Bさんとの税負担の差が無くなりました。
ただし、どのような所得でも平均課税制度を使えるというわけではないそうです。
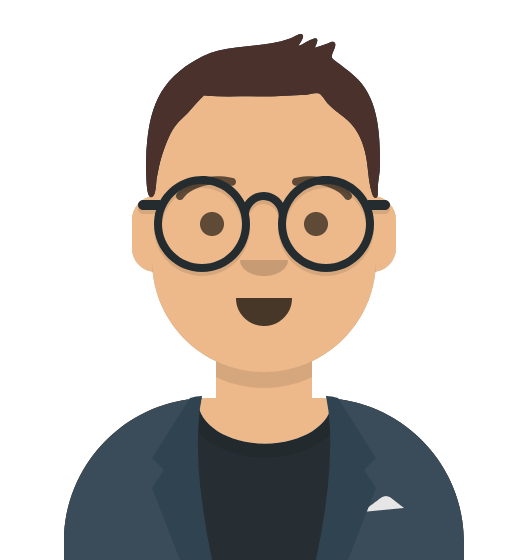
山林所得も毎年必ず発生するとは限らなかったり、利益がでるまでに長年かかったりする性質を考慮しての措置になります。
白色申告の場合の平均課税制度の適用について
適用することができれば、大きな節税効果が期待できる平均課税制度。私はこんな疑問を感じました。

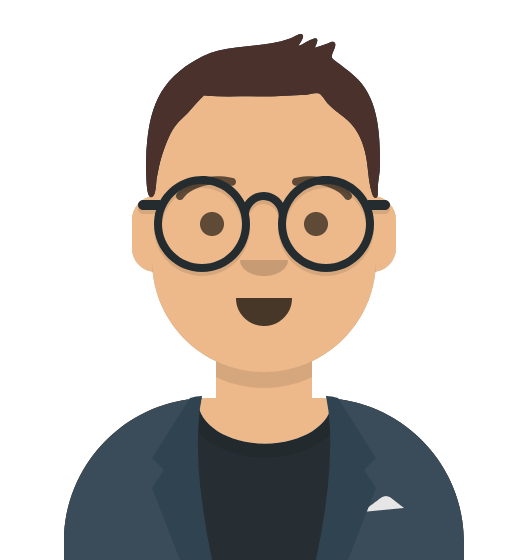

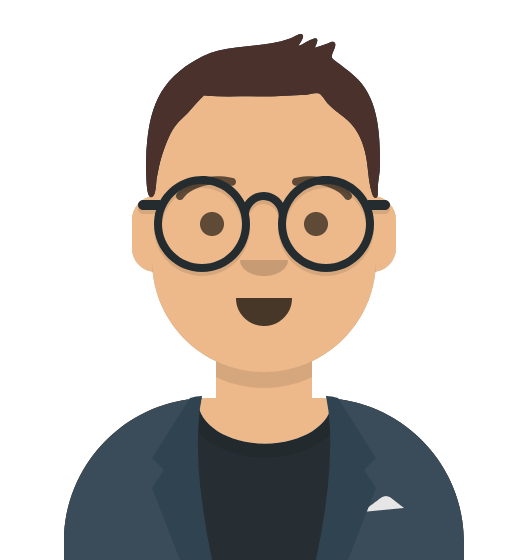
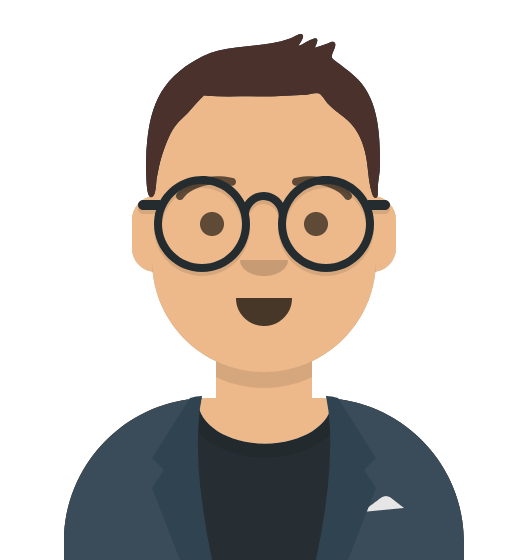

所得税のパートは以上となります。続いて、住民税についてです。
個人事業における住民税について
住民税の基礎知識について
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1年間の所得に対して課税される税金です。
1月2日以降に他の市町村に引越しても、1月1日現在で居住していた市町村に1年分の住民税を納付することになります。
給与所得者が他の市町村に引越した場合にも、最後の給与から一括で残りの期間分の住民税を天引きされたり、自分で納付する普通徴収に切り替わることになります。
住民税は所得に関係なく徴収される『均等割』と所得に応じて徴収される『所得割』からなります。所得割の税率は市町村民税(23区では特別区民税)6%と道府県民税(東京都では都民税)4%の合計10%になります。
住民税は課税タイミングが違う?!
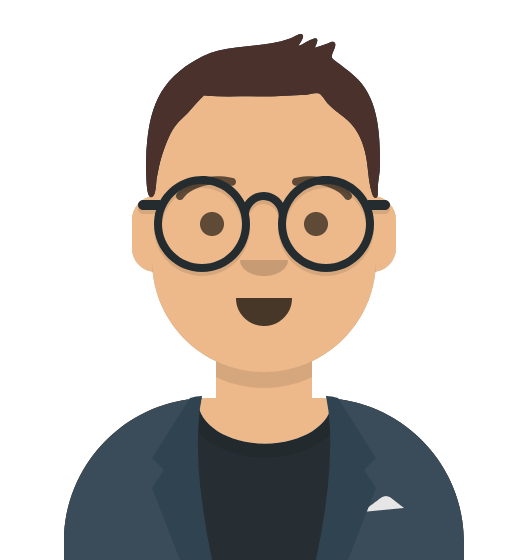

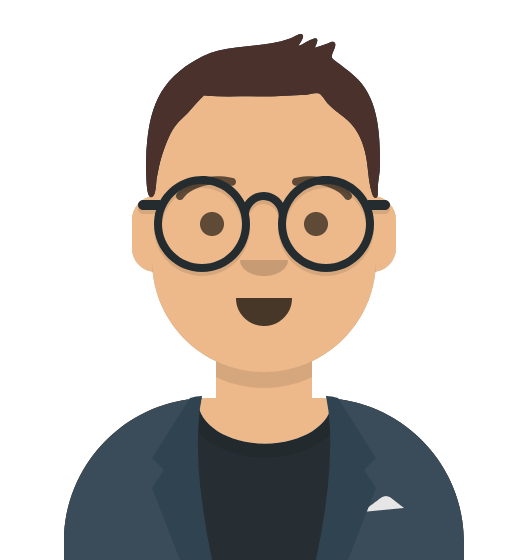
その税額は前年の所得をもとに計算されますので、去年は多く利益がでたけど今年はほとんど利益が無い。。。という場合にも関係なく住民税は払う必要があります。

有無を言わさず去年の利益分で住民税で支払う必要があるってことですね!
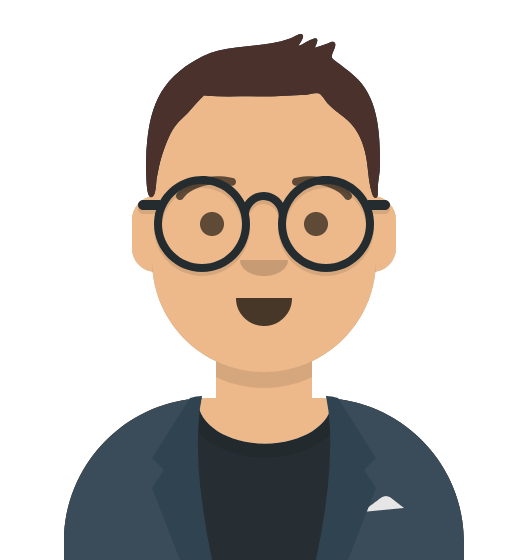
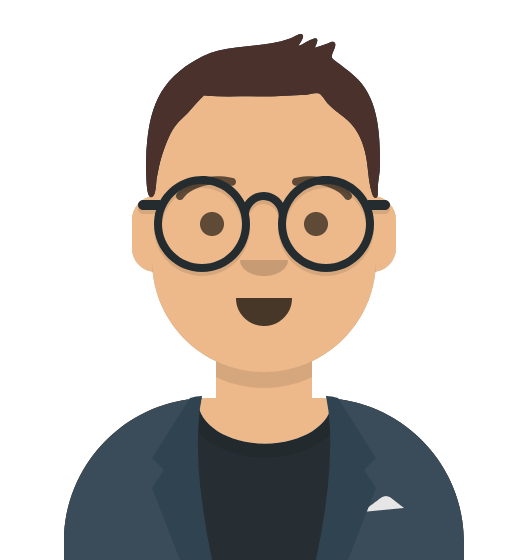

まとめ
- 所得税は、1月1日から12月31日までの1年間で得た利益に課される税金のこと
- 所得に対して高くなればなるほど段階的に税率が高くなる『超過累進課税方式』が採用されており、同じ所得でも税率が異なってくる場合もある
- 特定の年だけ所得が大きくなる場合に、税負担の不公平さを緩和させる『平均課税制度』がある
- 平均課税制度は青色、白色申告両方で利用できる
- 住民税は所得に関係なく徴収される『均等割』と所得に応じて徴収される『所得割』からなる
- 前年の所得が大きく、今年が少なかった場合でも、前年の所得に合わせて住民税を支払う必要がある
- 住民税を経費にすることはできない
所得に応じて税金を支払う必要がある日本の税法。正しい税金の知識があれば、多く税金を支払う必要がないことがお分りいただけたかと思います。もちろん税金を支払いたくないからといって、滞納や支払わないのは犯罪になりますので、注意してください。
本稿では所得税と住民税について説明しましたが、所得税や個人事業税について気をつけるべきポイントを知りたい方は下記の記事をご覧ください。